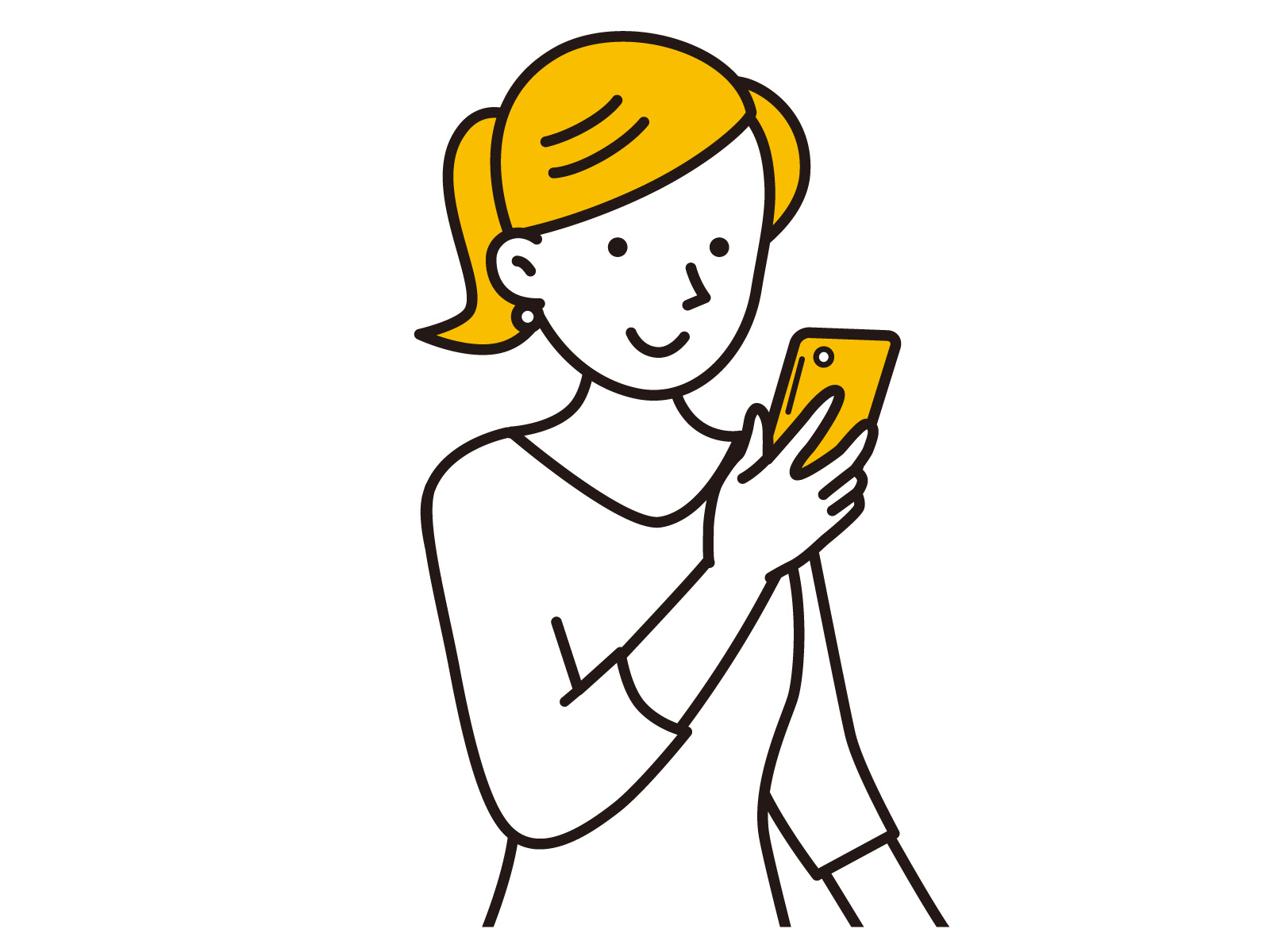総務省が昨年公表した住宅・土地統計調査(2023年)によると、全国の空き家数は同年10月1日時点で900万2000戸に上り、過去最多を更新した。所有者の高齢化や核家族化を背景に、賃貸用や別荘などを除いた放置空き家の問題が深刻化する。空き家の事情はさまざまで、適正な管理や利活用には地域の実情に応じた支援が欠かせない。増える空き家をどうするか、各地で模索が続く。
太田市に相談所を設けるNPO法人よろずや余之助の桑原三郎さん(75)の元には、15年ごろから管理や相続に関する問い合わせが増えた。幅広い問題に対応しようと、19年に専門家と連携した「県空き家対策プロジェクト」を立ち上げ、個々の状況に合わせた解決策を探る。
◎後期高齢者
背景には、持ち家率の高い団塊世代が後期高齢者となり、転居や死亡によって使われない住宅が増えている状況がある。草木が生い茂って隣家や道路にはみ出したり、登記が更新されていないため相続人を探したりと「対処にかかる時間は長くなっている」と危機感を抱く。
桑原さんが適切な策のヒントにするのは、何げない会話。「地域の困り事は地域で解決するのが良い。気軽に相談できる場があることが大切」と話す。
空き家の増加傾向は県内も同様。総務省の23年調査では、本県は過去最多の16万1千戸で前回調査(18年)から3千戸増えた。そのうち別荘や賃貸、売却用を除いた使用目的のない空き家が7万3千戸を占める。
管理の行き届かない空き家は、災害時に倒壊する恐れや不法侵入、景観の悪化といった問題が指摘されている。政府は23年12月に施行された改正空き家対策特別措置法で、空き家への課税を強化するとともに、危険な状態になる前の撤去などを促す仕組みを設けた。
自治体が空き家物件の情報を集めてホームページ(HP)で公開する「空き家バンク」は全国的に広がるが、県内では数件~十数件程度の掲載にとどまるケースが多い。ある自治体の担当者は「公的機関が管理できるわけではなく、載せるメリットがないと判断されている」とみる。
◎近所への影響
「所有者は誰にでも貸したいわけではない。近所にどういった影響を及ぼすのかを考える」。中之条町移住・定住コーディネーターの村上久美子さん(40)は指摘する。
16年からコーディネーターとして移住希望者と空き家のマッチングを進め、首都圏などからの定住につなげている。移住者は徐々に増え、23年末時点で227人が暮らす。
村上さんは地域の意見を最優先に考え、移住希望や希望者本人を地域に紹介するなどしてマッチングを進めている。希望者の側には意向をしっかり確かめ、山間部で暮らせるかや地域との相性を慎重に見極める。「自分の家も残り、『使ってもらえて良かった』と喜ばれる」と話す。
放置したままの空き家は数年で劣化してしまう。村上さんは「相談できる窓口を明確に設けることが必要。チーム化して問題解決できる実力を付けたい」と展望する。