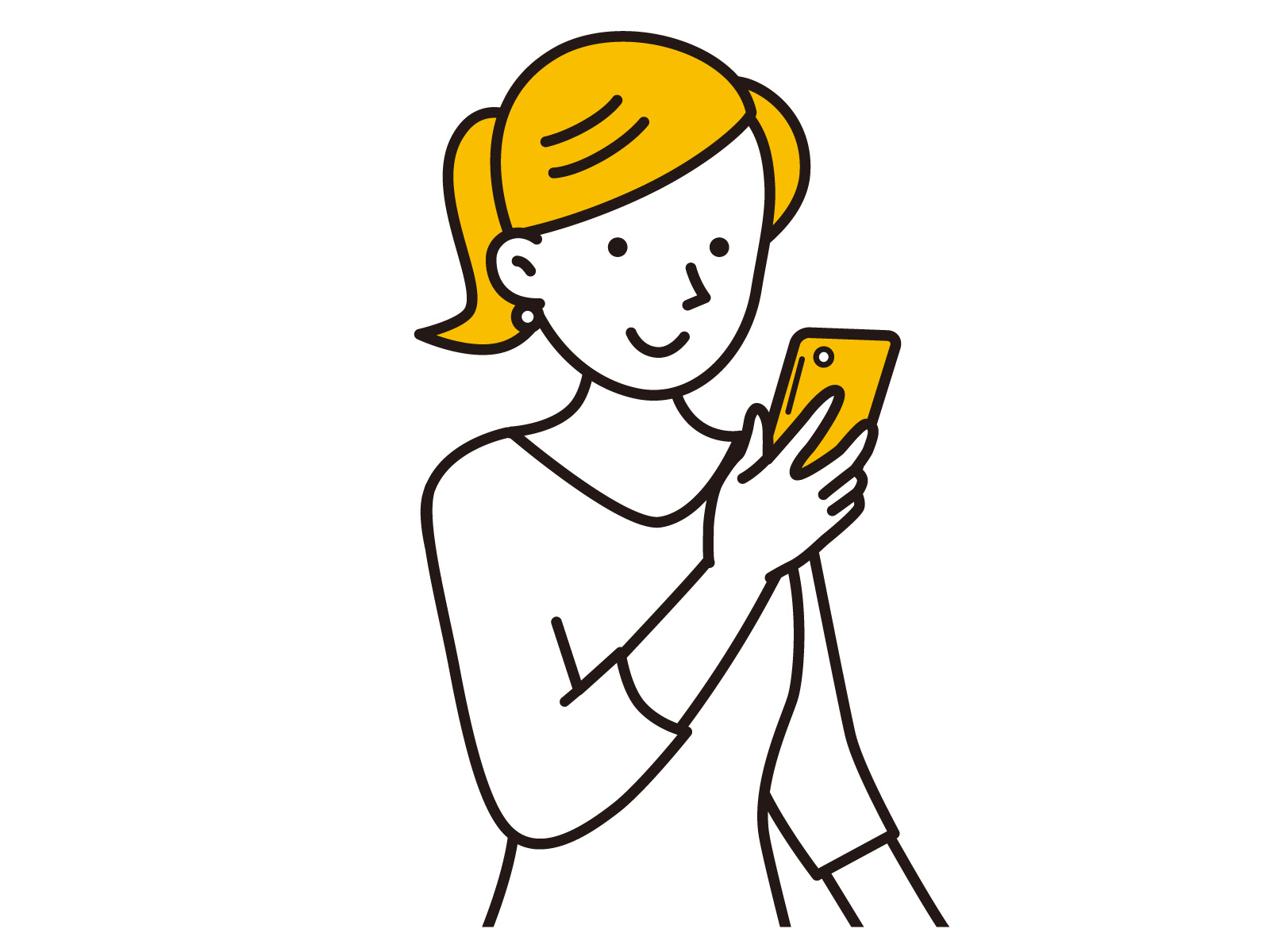今月13日の昼過ぎ。高崎市内の空き家を活用した集いの場「よっちゃん家(ち) 井野川」に、地元住民ら10人ほどが集まった。食事を楽しんだり、体を動かしたりするひとときを過ごした。
「よっちゃん家」は地域の居場所として、2021年に活動をスタートした。施設は築45年の木造2階建てで、代表の池田優子さんが7年間空き家だった叔母の家を改修。親族らと家財の整理や庭の手入れをし、地域サロンの改修を補助する市の制度も活用して、手すりを設けたり玄関を修繕したりした。
池田さんの仲間の元看護師が集まって運営組織を立ち上げ、23年にNPO法人化した。高齢者らが運動したり、手作り料理を楽しんだりする会や、食料支援が必要な人を支える「フードパントリー」などを実施。池田さんは「気軽に集まって楽しみ、本音が話せる、そんな場所をつくりたい」と話す。
同市では空き家を利活用した地域サロンが増えている。昨年までに32件が同様の助成を受け、空き家の改修につながった。
利活用が広がる一方で、多くの人が頭を悩ませているのが相続だ。住宅所有者の高齢化が進み、不動産の相続案件も非常に増えていることから「家じまい」にも関心が高まる。
国土交通省が19年に実施した調査によると、空き家の取得経緯として最も多かったのが相続で55%。取得した人の約3割が車、電車などで1時間以上かかる遠隔地に住んでいるという現状も浮かび上がった。空き家にしておく理由は「物置として必要」が最多で、「解体費用をかけたくない」「さら地にしても使い道がない」が続いた。
行政書士高崎事業協同組合は空き家に関する無料相談会を開いている他、出張相談にも応じる。同組合の行政書士、広兼喜久恵さんは「家を持つことが当たり前の時代が変わり、地縁も希薄になった。管理の大変さもあり、不動産を処分したいという相談が増えた」と実感する。
家じまいに当たり、広兼さんは「まず所有者が家を将来どうしたいのか、考えてほしい」と話す。その上で、不動産に関する書類の整理を進め、状況を相続人に伝えておく必要があるという。
具体的には、固定資産税の納税通知書や登記簿で権利関係や所在地を確認すること、家族との話し合い、遺言書作成の必要性を挙げる。遺言書は「あらゆるケースで役立つ。心配事を残さないよう、前向きに捉えて作成してもらいたい」と強調する。
空き家を整理するには費用がかかる。広兼さんは所有者も相続した人も「不動産を後回しにせず、考えてほしい」と、専門家への相談を呼びかける。
【記者の視点】
◎地域に応じた仕組みを
空き家の問題は複雑だ。遺品や家財があったり、建物の価値が低かったりして売却が難しい。解体に多額の費用がかかり、更地にすれば固定資産税が上がる。所有権を国に移すことができる相続土地国庫帰属制度もハードルが高い。そうした事情から所有者は解決策を見いだせず、時間だけが過ぎていく。
管理不十分な空き家が増えれば、地域全体の荒廃につながり、空き家は「個人の問題」と割り切れない時代になった。地域事情に応じた対応が必要で、空き家の利活用や管理の仕方をイメージできるような仕組みづくりが求められる。